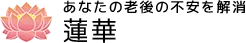経済的に困窮してしまった日本国民が、誰でも申請できるセーフティーネットといえば「生活保護」です。さまざまな事情で生活保護の受給をお考えの方もいるでしょう。
生活保護とは何か基本となる考え方、必要な手続き、申請の注意点などわかりやすく解説していきます。これから生活保護の受給をするときに参考にしていただけますと幸いです。
生活保護とは

生活保護とは、受給者が経済的に自立することを目的に行われる「生活保護制度」によるものです。日本国憲法第25条では「すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定められています。
何かしらの理由で生活困窮者となった人に対して、自立するための仕組みでもあるのです。
生活保護には「基本原理」と「基本原則」という2つの支えがあり成り立っています。
それぞれ、具体的に見ていきましょう。
基本原理4つ
生活保護法における基本原理は、以下4つのことをいいます。
1.国家責任の原理
2.無差別平等の原理
3.最低生活の原理
4.保護の補足性の原理
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.国家責任の原理
生活保護の最も根本的な原理となり、生存権を実現するために国が責務として困窮している国民の保護を行うことをいいます。
生活に困窮しているすべての国民に、経済的な自立が出来るように国が支援するということです。
2.無差別平等の原理
国民すべてが、法の定める要件を満たしている限り無差別平等に保護を受けられます。生活困窮者になった理由や社会的な身分は関係ありません。
法の定める要件とは、犯罪等を犯すことなく法律を守って生活しているという意味を持ちます。
3.最低生活の原理
法で保障されている最低生活水準について、健康で文化的な最低限の生活を維持できることを保障しています。
最低限の生活に対しての考え方は人によっても尺度が異なるため、最低限の生活が健康で文化的であることを定義づけ、受給者の生活水準を維持しています。
4.保護の補足性の原理
保護を受ける側である国民に要請される原理のことをいいます。各自が持っている能力や資産、他の施策を使い最善を尽くしても、最低生活が維持できない場合に生活保護制度を活用することができます。
生活保護は、誰でも受給できるものではなく最後のセーフティーネットでもあるのです。
※生活保護法の基本原理と基本原則
基本原則4つ
1.申請保護の原則
2.基準及び程度の原則
3.必要即応の原則
4.世帯単位の原則
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1.申請保護の原則
生活保護を受給するためには、必ず申請の手続きが必要です。要保護者・扶養義務者・同居の親族の申請に基づき行われるものとしています。
ただし、要保護者の緊急性が高い状態にあると判断されたときは、申請をせずとも必要な保護を行うこともできます。
2.基準及び程度の原則
厚生労働大臣によって定めた要保護者の需要を基にしています。
金銭または物品で満たせない不足分を補う制度において行われるものになり、年齢や性別、世帯構成などの事情を考慮して決められます。
最低限度の生活の需要を満たすもので、超えてはいけません。
3.必要即応の原則
生活保護は不正受給を防止するために、要保護者の年齢・性別・健康状態などを基に行政が的確に判断します。実際に必要だと認められれば、迅速に決定することをいいます。
4.世帯単位の原則
生活保護は世帯で受給するため、世帯のうちの1人だけで受給することはできません。
ただし、特別な事情がある場合は世帯分離を認めています。個人を世帯の一つとすることで、個人受給が認められる場合もあります。
生活保護を受給するための3つの条件

生活保護は、生活困窮者に対し国が最低限度の生活を保障し、経済的な自立を促す支援であることがわかると思います。
生活保護には受給できる期間は定められていないため、病気や障害が原因で最低生活費以上の収入を得るのが難しい人や年金だけで生活するのが難しい人も要件を満たせば受給しています。
生活保護を受給するための3つの条件を説明します。
・最低限の生活費に満たない収入であること
・親族から経済的な援助が見込めないと判断されること
・資産や貯金のような売却できるものがないこと
それぞれ詳しく見ていきましょう。
最低限の生活費に満たない収入であること
収入が、最低限の生活費に満たない人は健康で文化的な最低限度の生活を送れていないことになります。
就労や年金による収入が、生活保護を受給した場合に支給される収入よりも少ない場合が対象です。収入とは、給与・賞与、農業収入や自営業の収入だけでなく、年金、贈与、不動産による財産や、保険給付金など幅広く該当します。
収入がある場合は差し引いた不足分が支給される仕組みです。
親族から経済的な援助が見込めないと判断されること
親族から経済的な支援が見込める場合は、生活保護の対象にはなりません。
親族が健康で文化的な生活を送っているのが理由で受給できないのではなく、経済的な援助を継続的に受けられるかどうかです。
要保護者が生活保護を申請すると、3等身以内の親族に「扶養照会」で確認が行われます。あくまでも援助の意思を確認するものなので、強制力はありません。
資産や貯金のような売却できるものがないこと
生活保護は働けるのであれば働き、活用できる資産があれば活用するのが基準です。
それでも、生活困窮者から抜け出すのが難しいと判断したときに、生活保護が受給できるようになります。資産や貯蓄のように売却できるものがある人は対象外になってしまいます。
生活保護を受ける人が得られる権利とは
決定された生活保護は、正当な理由なく止める・減らすことができません。
また、すでに支給されている保護の金品を受け取る権利は差し押さえの対象とならず、保護の金品には税金がかからない仕組みとなります。
ただし、資産があるのに生活保護を受給している場合や、就労について申請がないときは保護費を返還しなくてはいけない場合も出てきます。
例えば、保有していた不動産、生命保険を解約したことで得た収入などが対象です。
不法な手段によって生活保護の受給をしていた場合は、加算金や返還だけでなく、懲役や罰金が科せられることもあります。
生活保護の8つの扶助

生活保護は、健康で文化的な最低限の生活費を支給するだけではありません。
受給者が生活していくうえで必要となるさまざまな支援を受けることも可能です。
地域による差も出てきますが、生活保護には8つの扶助があります。
・住宅扶助
・生活扶助
・医療扶助
・出産扶助
・介護扶助
・教育扶助
・生業扶助
・葬祭扶助
それぞれ詳しく見ていきましょう。
住宅扶助
住宅扶助は、受給者が居住するための「家賃」のことをいいます。生活保護を受給すると、資産となる持ち家を所有できなくなるため、賃貸物件で生活することになります。
お住いの地域によって定める等級の違いや、世帯人数によって金額が変動します。なお、住宅扶助には上限が定められており、住宅扶助の上限を超える家賃では居住が認められていません。
また、生活保護で転居が必要になった場合、高額な転居費用を払うのは現実的ではありません。一時扶助として生活保護費から負担される場合もあるため確認してみてください。
生活扶助
生活扶助は、受給者が生活していくために必要な費用です。支給される扶助のなかで、明確な用途がなく使えるものになり、日々の食費や光熱費、被服をもとに算出しています。
生活扶助は、食事のように個人的にかかる費用(第1期)、世帯共通費用(第2期)を合算して算出していきます。お住まいの地域や受給者の年齢、世帯構成によっても異なります。
医療扶助
医療扶助は、受給者が医療サービスを受けるための費用です。
健康で文化的な生活を送るために、お金がなく医療機関が受診できないのはあってはいけないことです。現金で受け取れるものではなく、福祉事務所より医療券や調剤券が届きます。
指定の医療機関で提示すると無料で受診できる仕組みになります。ただし、病院によっては生活保護対象外の場合もあるため、事前に確認しておくのをおすすめします。
また、医療扶助のなかには治療材料費もあるため、眼鏡なども対象になり支給される場合も考えられます。
出産扶助
出産扶助は、生活保護受給者が出産するときにかかる費用を扶助するためのものです。
分娩費用や産後入院するための費用のことをいいます。病院にて出産するときは入院助産制度があるため、不足している分を費用で補う仕組みとなります。
自宅や医療施設ではない場所で分娩したときも居住分娩として認められます。他にも出産に伴う包帯やガーゼなどの衛生材料費や、おむつやミルクなどの出産準備費用も支給される場合があります。
介護扶助
介護扶助は、40歳以上の受給者であり要介護認定を受けた場合に介護サービスを受ける費用を補うためのものです。
基本的には介護保険サービスの7割以上は介護保険にてまかなわれています。残りが自己負担として支払うことになりますが、受給者の場合難しい場合も多く、介護扶助にて賄うことができます。
福祉事務所にて発行される介護券を使って、介護サービスが受けられるようになります。
教育扶助
教育扶助は、生活保護世帯の児童が義務教育を受けるために学用品費用を賄うための扶助です。
小学校に入学したタイミングから中学校を卒業するまでの9年間、扶助として受けられるものです。対象となるのは、学用品・教材・学級・課外活動参加費・学校給食などの費用となります。
教育扶助は義務教育までが対象となるため、高校生からは生業扶助の扱いとなります。
生業扶助
生業扶助は、受給者が経済的に自立するための費用です。就職活動や職業訓練を受ける費用などが対象です。
受給者自身が、自分の能力を活かしながら、持続可能な職につくための費用です。他にも自営業の開業に必要な費用も含まれます。
受給者の能力を高め、自分にあった仕事を見つけるためにも欠かせない費用といえます。
葬祭扶助
葬祭扶助は、受給者が亡くなり遺族も生活保護を受けているなど、葬儀費用を負担するのが難しいときに申請できる費用です。
葬祭扶助を使い葬儀を行うことを福祉葬といいます。対象となるのは、検案や運搬、火葬・埋葬・納骨が対象です。
ただし、告別式や通夜にかかる費用は対象外となり、自分で負担しなくてはいけなくなります。
生活保護を受けるために必要な手続き

生活保護を受けるためにはさまざまな手続きを行う必要があります。
具体的にどのような手続きが必要になるのか詳しく見ていきましょう。
1.お住まいの地域の民生委員や福祉事務所に相談する
お住まいの地域の民生委員や福祉事務所にて受給したい希望を伝えます。福祉事務所は都道府県や市に設置義務があり、町村は任意で設定されています。
役所に相談の窓口が設けられている事が多いので、相談も含め足を運ぶようにしましょう。
決められた住所がない(ホームレスなど)場合は、最寄りの福祉事務所にて生活保護の申請もできます。
2.申請手続きをする(必要な書類)
生活保護の申請のためには、たくさんの書類を書かなくてはいけません。
はじめて見る書類が多いのもあり、書き方で戸惑うこともあると思います。
具体的には以下のような書類を書くことになります。
・生活保護申請書
・収入申告書
・資産申告書
・同意書
・生活歴
・扶養義務者届
書類はすべてを埋める必要はないものの、できるだけわかる範囲で記載するようにしましょう。
ただし、虚偽の記載をして発覚した場合は、申請を受付できなくなってしまうこともあります。
生活保護を受給したい理由は真実を記載するようにしましょう。
3.担当員(ケースワーカー)が調査をする
生活保護の申請を行うと、福祉事務所のケースワーカーがさまざまな調査を行います。
具体的な内容としては、現在の生活状況である収入や資産の有無を確認します。親族や世帯員の状態、今までの生活状況など必要に応じて確認していきます。
より調査が必要になる場合は、金融機関や保険会社に照会することもあります。
4.調査結果を元に保護が必要かどうか判断する
ケースワーカーの調査結果を基に、生活保護が必要かどうか判断していきます。
国が定めている基準により保護が必要かどうか、どの程度か福祉事務所が判断していきます。生活保護の申請が受理されるまでに原則14日以内と決められています。
また、申請を希望する人によって状況も変わってくるため、緊迫している人を優先的に受理する必要もあります。
5.通知が届きます( 保護開始決定通知書・保護申請却下通知書)
調査結果をもとに保護開始決定通知書・保護申請却下通知書のいずれかが届きます。保護が決定すると、生活保護受給者証が届きます。
生活保護受給者だけに発行される身分証のような役割を持っているものになり、受給証明として使います。
個人情報も記載されているため紛失しないように気を付けましょう。もし、紛失してしまったときは役所にて再発行も可能です。
担当のケースワーカーに相談して、再発行に必要な手続きを行うようにしてください。
6.受給開始(直近の支給日から保護費の支払が始まる)
生活保護の審査に通過すると、直近の支給日から保護費が開始となります。地域ごとに支給日が異なり、保護決定通知書にて通知を受けた金額が振り込まれるようになります。
自治体によっても変わってくるため、振込のタイミングも確認しておくと安心です。
・不服があるときは県知事に対して審査請求を行う
生活保護に関する決定に不服があるときは、都道府県知事に審査請求を行います。
また、都道府県知事が行った裁決に対して不服があるときは、厚生労働省大臣にて再審査請求を行いないます。決定を知った翌日から起算して3か月以内に審査請求を行う流れです。
生活保護が増額する加算には何がある?

生活保護費は地域によって決まっていますが、一定の基準を満たしている場合に、生活保護費が増額することもあります。
生活扶助に加算されるものになり、用途が定められているものではありません。生活に使える費用が増えることになります。
以下の9種類の加算が該当します。
・妊産婦加算
・母子加算
・児童養育加算
・障害者加算
・在宅患者加算
・介護保険料加算
・放射線障害者加算
・介護施設入所者加算
・冬季加算
それぞれ詳しく見ていきましょう。
妊産婦加算
妊産婦加算は、妊娠中の女性や産後の生活保護受給者を対象にした加算です。
生活費は、栄養補給などの用途で加算されるようになります。
母子加算
母子加算は、ひとり親世帯が生活保護を受給したときにされる加算です。父子家庭も対象になり、子どもの人数と地域の等級によって変動します。一般的には児童が18に達した日以後の最初の3月31日までが対象です。
障害者加算の対象になる児童は20歳になるまでなどケースによっても変わってきます。また、児童を養育している人が再婚すると受給できなくなります。
児童養育加算
児童養育加算は、18歳未満の児童のいる生活保護世帯に養育費として加算されるものです。
子どもの健全育成費用を目的に学校外活動費用を補填するものとして支給されます。支給される金額は一律で決まっており、10,190円です。18歳になる年度の3月31日まで支給される加算です。
障害者加算
障害者加算は、精神障害者もしくは、身体障害者が生活保護を受給するとき加算されるものです。
障害者等級1級もしくは2級または、国民年金法施行令別表にて定めた障害のあるものが対象です。
また、障害者等級3級または、国民年金法施行令にて2級のいずれかに該当する障害のある人が対象となります。
在宅患者加算
在宅患者加算は、在宅で療養している患者に対して支給される加算です。療養に専念するために追加として必要となる栄養補給などの経費を補填する目的があります。
介護保険料加算
介護保険料加算が、介護保険第1号保険者である受給者に対して支給されるものです。介護保険料は生活保護でも対象となるため、経費を補填するために実費で支給されます。
放射線障害者加算
放射線障害者加算は、放射線によって障害のある受給者に対して行うものです。
現在の羅患者と元羅患者によっても支給される金額も変わってきます。
介護施設入所者加算
介護施設入所者加算は、介護施設に入所している受給者に対して支払われるものです。
理美容などの裁量的経費を補填するものになり、恰好品なども対象となります。介護施設入所者加算を受けることで、施設にて提供されているサービスの質も向上し専門的なケアも受けられます。
より快適な生活を送ることが可能になるための加算といえるでしょう。
冬季加算
冬季加算は、暖房費用として支給されるものです。地域によっても必要な費用が変わってきますが、寒くなってくる10月~4月の間に支給されるものです。
生活扶助に加算されるため、用途を制限するものではありません。全国の生活保護の受給者に支給されるものになり、暖かい地域に住んでいる人も支給されます。
生活保護の申請で気を付ける事

生活保護の申請において気を付けるべきことをまとめて紹介します。
・担当員(ケースワーカー)に協力する
・受給できる金額は地域によって異なる
・支給日も地域によって異なる
・保護費で借金の返済はできない
それぞれ詳しく見ていきましょう。
担当員(ケースワーカー)に協力する
生活保護を受給すると、担当のケースワーカーがつき、定期的な家庭訪問を行います。
受給者に対して生活環境を把握することはもちろん、申請時と異なる点がないかを確認する目的があります。
受給者が生活保護を受けられるように適切な指導を行っていることもあり、素直に従い協力する姿勢を見せることも大切です。
指導に対して非協力的な態度をとっていると、生活保護の審査に通過できなくなる恐れも出てきます。ケースワーカーの話をしっかりと聞き、協力する姿勢を見せるようにしてください。
受給できる金額は地域によって異なる
生活保護で受給できる金額は、お住まいの地域によっても異なります。いずれの場合にしても該当の地域で暮らしていく最低限の金額が支給されるようになります。
地域によっても物価や家賃などの最低限の基準が変わるため、どこで生活保護を受給しても平等な生活が保証されるように地域差をつけています。
東京23区など主要都市は生活保護費が高めに設定されています。他にも加算される条件に該当する場合は、支給額が高くなります。
支給日も地域によって異なる
生活保護の支給日は、毎月決められた日付です。自治体ごとに設定されており、休日と重なった場合は前後することもあります。
一般的には月初に支給されることが多いのですが、自治体によっては月末の場合もあります。ただし、医療扶助や介護扶助は施設に直接支払う為、支給日は関係なくいつでも利用できる仕組みです。
受給が決まったとしてもすぐに支給されるわけではないため、待たなくてはいけない場合もあります。
保護費で借金の返済はできない
生活保護費で借金の返済に充てることはできません。そもそも受給者になるとローンの審査に通りにくくなり新規で借金をするのは現実的に考えても難しくなります。
生活保護費は税金より賄われているお金になるため、借金の返済=個人の借金を返済することは生活保護法にて禁止されています。
トラブルの原因になってしまうことも十分に考えられるため、生活保護を受給しているときに借金を作らないようにしておきましょう。
すでに借金があり生活保護を受給することはできないわけではありません。生活に困っている分は生活保護費で賄い、借金は債務整理を行うなど別の制度を行います。
まとめ
生活保護費の仕組みについて、基本となる考え方や手続きの流れについて説明しました。
生活保護はお住まいの地域や世帯によっても受給額が変わってきますし、加算できる対象があるかどうかの違いも出てきます。
生活保護を受給する場合、まずは福祉事務所に相談に行き必要な手続きを確認するようにしてください。
受給するためにはケースワーカーとの関係性も重要になりますし、生活保護法を遵守しなくてはいけません。
生活保護についてもっと知りたい、申請をしたいと思ったらまずは相談に行き必要な手続きを確認するのをおすすめします。
プロフィール

- 一般社団法人蓮華は高齢者様を一人にさせず、一人一人に対して真心を持って接していく会員制の団体です。 直面している社会問題を寄り添い共に考え、より良い未来を作り、 人生を豊かにしていくサポートを行っていきます。
最新の投稿
 生活支援お役立ちコラム2025.02.21一人暮らしの生活保護受給者が知るべき支援制度と毎月の金額の目安
生活支援お役立ちコラム2025.02.21一人暮らしの生活保護受給者が知るべき支援制度と毎月の金額の目安 生活支援お役立ちコラム2025.02.21生活保護で賃貸住宅を借りる際のポイントと家賃補助の仕組みを解説
生活支援お役立ちコラム2025.02.21生活保護で賃貸住宅を借りる際のポイントと家賃補助の仕組みを解説 生活支援お役立ちコラム2025.02.21生活保護は毎月いくらもらえる?収入と扶助内容の詳細を解説
生活支援お役立ちコラム2025.02.21生活保護は毎月いくらもらえる?収入と扶助内容の詳細を解説 生活支援お役立ちコラム2025.02.21生活保護医療券の使い方と注意点!受給者が知っておくべき医療サポート
生活支援お役立ちコラム2025.02.21生活保護医療券の使い方と注意点!受給者が知っておくべき医療サポート