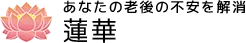生活費が足りず、生活保護の申請を検討している人もいるのではないでしょうか。
生活保護の受給者は、25万件を超え年々増加傾向にあります。生活に困窮している人のセーフティーネットとしての役割も持っています。
生活保護を受給するためにはどんな申請方法が必要になるのか、審査で覚えておきたいポイントもあわせて解説していきます。
生活保護の申請を希望している人やご家族は参考にしてください。
最寄りの福祉事務所に行って申請の意思を伝える

生活保護を受給したいときは、自宅の最寄りにある福祉事務所の窓口に行き受給したい意思を伝えます。福祉事務所とは、社会福祉法14条にて規定された事務所のことをいいます。
生活に困窮した人に福祉制度の情報を提供し、支援の案内を行っています。面談を行い、支援を使い解決することが難しいと判断したときは、生活保護を検討する流れです。
福祉事務所は全国1,250カ所設置され、厚生労働省のHP記載の以下より確認できます。
自宅の管轄の福祉事務所を調べたうえで、実際に足を運ぶ流れです。
最寄りの福祉事務所がわからないとき
福祉事務所について調べたものの、最寄りがわからない人もいるかもしれません。
その場合、近くにある市役所や区役所にて相談するのをおすすめします。
また、福祉事務所は通称であり「生活保護課」などの名称で呼ばれていることもあります。市役所や区役所にて「福祉事務所はどこですか?」と場所を聞けば教えてくれます。
なお、福祉事務所を設置していない町村の場合もあります。
その場合は、お住まいの町村役場でも申請可能です。
申請後にはお住まいの地域を所轄する、福祉事務所に情報が送付される仕組みです。
窓口の担当者より聞き込み
現在の就労状況や経済的なことを聞き込みします。
結果、生活保護が必要であると判断された場合は、申請書を受け取りその場で記入して提出する流れです。生活保護の申請は決められた形式以外にも、事前に印刷した用紙に記入しても問題ありません。
生活保護は世帯単位で申請する
生活保護は世帯単位での申請が基本となります。
世帯の基準は、生計を共にしている人達であり、生活保護の対象となります。実際に申請書を出すときに世帯全体がわかるように記載する必要があります。
ただし、事情によっては世帯では個人で申請できるように考慮される場合もあるでしょう。事情も踏まえて福祉事務所にて相談するようにしてください。
生活保護の申請に必要なもの

生活保護の申請には、必要な書類を福祉事務所にて提出する必要があります。
特別な事情がある場合に限り口頭での説明にも対応しています。
主な申請書の種類
申請書の書類は以下の種類です。
1.生活保護申請書
2.収入申告書
3.資産申告書
4.同意書
5.生活歴
6.扶養義務者届
7.一時金申請書(必要に応じて)
書類は、福祉事務所にも置いてありますがダウンロードもできます。
それぞれどのような書類か詳しく見ていきましょう。
1.生活保護申請書
生活保護申請書は、文字通りに申請するための書類です。
記入する内容は基本的な個人情報を記載するものになり、申請者の住所や氏名・電話番号・家族構成・本籍地などです。
生活保護申請書の裏側には、申請理由を記載する場所もあります。あくまでも簡潔でいいので、どうして生活が厳しくなってしまったのか、正直に記載するようにしましょう。
項目ごとに記載していくだけなので、そこまで書き方が難しく感じることはないと思います。
2.収入申告書
収入申告書は、収入がどの程度あるのか記載するための書類です。
仕事の内容や勤め先、前3か月分の給与(見込み)、就労状況なども記載します。また、成人していて収入がない家族がいるときは、名前と働いていない理由を記入することもあります。
収入とは、給与などの働いて得たものだけでなく、年金や養育費、仕送りなども対象です。毎月、どのくらいの収入を受け取っているのか抜けなく記載しましょう。
3.資産申告書
資産申告書は、所有している資産を記載するための書類です。
土地・建物、預貯金、有価証券・生命保険などの資産状況を記載します。
また、自動車の所有情報について記載する場所もあるため、所有しているときは忘れずに記載しておきましょう。
他にも債務や債権がどの程度あるのかなど収支を把握するために必要な書類です。
4.同意書
同意書は、銀行口座や信託会社の情報照会に同意するための書類です。
一定以上の収入や預貯金があると、原則として生活保護を受給できません。そのため、生活保護を申請するときに銀行口座などの情報を確認し、申請している内容に相違がないかどうかを確認します。
また、受給後もお金の収支が怪しいと感じれば、いつでも確認できるための同意書です。
記載する内容は氏名や住所などの一般的なものです。
5.生活歴
生活歴は、受給希望者のこれまでの人生についてざっくりとまとめた書類です。
細かく調査を行うわけではないので、大まかなもので問題ありません。学歴や就労の有無、結婚歴などの情報を記載していきます。
記入した内容をもとに、ケースワーカーが自宅を訪問してより詳しい話を聞くようになります。申請する全員の情報を記載するようにしてください。
6.扶養義務者届
扶養義務者届けは、名前の通り扶養義務のある人の氏名や住所、生年月日などの連絡先を記載するものです。
単身者や扶養義務者がいないときは何も書く必要はありません。書類の一番下にある、上記の通り相違ありませんの場所にあなたの情報を記載するだけです。
7.一時金申請書(必要に応じて)
一時金申請書は、アパートに入居するための費用や進学・入学準備費用など臨時的に必要な費用を支給してもらうための書類です。
生活保護の受給を希望している人にとって、必要な費用とはいえど捻出するのは現実的ではありません。福祉事務所の窓口にて手続きを行うようになるため、引越しを考えている人は申請書を用意しておきましょう。
申請のときに持っていくもの
生活保護の申請のときに必ず必要になるものではありませんが、手続きをスムーズに進められる可能性も出てきます。念のため用意しておくのをおすすめします。
1.通帳
2.印鑑
3.写真付きの本人確認書類
4.収入がわかるもの
5.賃貸借契約書(現在の住まいの状況がわかるもの)
生活保護の申請をしたあと住まいはどうなる?

生活保護の申請をしたあとに、住まいがあるかないかによって変わります。
今住んでいる家があるときは、そのまま家に住み続けることになることが多くなります。
ただし、家賃が高額過ぎるなど例外的な条件によって引越しが必要になることも考えられます。
住まいを持っていない人は、一時的な待機場所にて過ごしアパートに入居します。
生活保護受給者向けの公的・民間の施設があるため、宿泊先として利用します。
その後、アパートに入居することになりますが、入居費用は生活保護制度で支給されるので安心です(地域差あり)。
ただし、自分から伝えないと制度を使えない場合もあるため確認しておきましょう。
生活保護の審査にも種類がある!

生活保護を受給するためには、審査を受けなくてはいけません。
生活保護を申請する人のなかには、不正受給の問題もあり大きな話題になっています。
そのため、生活保護を受給する場合は、虚偽申請がないか事前に調査を行っています。実際にどの程度の審査が行われるのか、解説していきたいと思います。
身辺調査
身辺調査は、申請者本人にはお金がなくても親族で援助できる人がいるか調査を行います。
生活保護は税金によって賄われているため、援助できる人がいれば頼れるかどうかの確認が行われます。これを扶養照会といい、生活保護では必ず行われているものです。
扶養義務者届をもとに3親等以内の親族に書面にて通知し、意思確認を行います。
扶養が難しい場合は、それ以上に追求される心配もありません。申請者のなかには家族に扶養照会を行うのが難しい状況も出てくるでしょう。
そのような場合、扶養照会を行わずに申請を進めることもあります。
ケースワーカーが自宅に伺い、生活環境の確認も行います。家の中に現金など高額なものがあるかどうかを確認します。あくまでも簡易的に確認になるため、細かくチェックすることはなくプライバシーを尊重してもらえます。
資産調査
資産調査は、預貯金口座や収入、資産、生命保険などを調べることをいいます。
預貯金や資産を所有している場合は、原則として受給できない仕組みです。預貯金の調査は、同意書にサインしているため、口座情報をいつでも閲覧できる権利を持っています。
受給したあとに預貯金があった場合は、保護費の返還を求められることもあります。
他にも、申告者名義の建物や土地、自動車などの資産を持っているかもしれません。
売却すれば、当面の生活費に充てることもできるでしょう。なかには、名義の実を変更してごまかす人もいるのですが、不正受給になってしまうリスクがあります。
資産調査は虚偽の申告をしないように給与明細なども用意しておきましょう。
定期訪問
定期訪問とは、生活保護を受給したあとに担当のケースワーカーが自宅を訪問することをいいます。頻度は地域や担当のケースワーカーによっても変わってきます。
受給者が働ける状態であるかどうか、同居している未申請のパートナーがいないかを確認します。同じ家に住んで生計をともにしている場合は、戸籍の手続きをしていないとしても世帯として考えます。
ケースワーカーに申告しない人もいるため、定期訪問で確認しています。
自治体によって受給しやすいかどうかの差がある場合も
自治体によって、受給しやすいかどうかの差は基本的にはあってはいけないことです。セーフティーネットであることを考えても、審査が甘い自治体というのは認められていません。
ただ、地域の特色によって変わってくる部分もないとはいえません。
例えば、地方の場合は持ち家率が高くなり移動手段として車も必要になってきます。そのため都心部と比べて生活保護の資産面では条件を満たしていないと言えると思います。
それでも、生活保護を受給している人もいます。
地域の特色によって多少の差が出てくる場合もあります。
また、福祉事務所の相談員によって多少の判断の違いもあります。自治体全体で甘いといえるわけではなく、相談員によって審査の考え方なども変わってきます。
生活保護の審査に落ちやすい特徴

生活保護の審査を受けたものの、審査に落ちてしまう人もいます。
ある程度審査基準が決まっているからこそ、予測できる部分ともいえるでしょう。
生活保護の審査に落ちやすい6つの特徴について説明します。
・働ける能力があり収入を得られる人
・年金や生活福祉資金貸付制度などで賄える人
・お金に変えられる資産を持っている人
・完済するのが難しい借金を持っている人
・家族などの親族から支援を受けている人
・ケースワーカーの調査に協力しない人
それぞれ、詳しく見ていきましょう。
働ける能力があり収入を得られる人
働ける能力のある人は、仕事をする義務があります。
働ける状態にあるにも関わらず「仕事をするのが嫌だから生活保護を受ける」という選択肢はありません。出来る限り仕事で収入が得られるように努力してみて、それでも働けない理由がある人が優先的に受給できます。
一時的に失業中で仕事ができない人も、働く意思がある場合、就職できるまでの期間限定で生活保護を受給できる可能性も出てきます。
年金や生活福祉資金貸付制度などで賄える人
年金や生活福祉資金貸付制度で、十分に生活できている場合は審査に落ちてしまう可能性も出てきます。
年金には病気やケガで生活に支障が出ている人向けの障害年金も選択できます。制度を活用することで生活費を賄える場合は、生活保護以外の選択をすることになります。
どんな制度が活用できるのか、相談してみるといいでしょう。
お金に変えられる資産を持っている人
建物や土地、自動車やバイク、高価な貴金属や装飾品など資産として判断出来るものを持っていると、審査に落ちやすくなります。自動車も資産ではありますが、身体に障害があり通勤や通院で欠かせないものだと判断される場合もあります。今住んでいる住宅も売却されるわけではなく、保有し続けることになります。資産と見なされる可能性のあるもので、どうしても手放せないものがあるときは、相談しておきましょう。
完済するのが難しい借金を持っている人
生活保護のお金を使い借金の返済はできません。
そのため、完済していない借金がある人は、審査に落ちてしまう可能性があります。ただし、必ずしも通らないわけではなく債務整理や自己破産で借金をなくすことを前提としている場合、申請は可能です。
借金が原因で生活が困窮してしまう人は、一度ケースワーカーに相談してみてください。対処法も含め提案してもらえるように相談に行くのをおすすめします。
家族などの親族から支援を受けている人
家族や親族から支援を受けられる人は、審査に落ちてしまう可能性も出てきます。
受けられる援助があるかどうかを確認したうえで、受けられるものはすべて受けなければなりません。ただし、援助を受けても最低限の生活に満たないときは生活保護が受けられる場合もあります。援助が受けられる場合は、審査に通るとは限りません。
ケースワーカーの調査に協力しない人
生活保護の審査では、ケースワーカーの調査に協力しない人も難しくなってしまいます。
本人確認書類の提出や、預貯金や収入についての書類を提出しない人もいます。非協力的だと判断されてしまうと、生活保護の申請が通りにくくなってしまいます。
ケースワーカーとは、長い付き合いになることも多いからこそ虚偽の申請をすることなく協力的な態度を見せるようにしていきましょう。
生活保護の申請から受給できるまでの日数

生活保護の申請をしてから、実際に受給できるまでの日数について見ていきましょう。
審査や資産調査を申請をした日より原則14日以内
生活状況や資産の審査を行ったうえで、申請し原則14日以内には結果がわかります。
一般的には生活保護の申請が受理されるまで10日前後の日数が必要になります。
ただし、明日食べるものがない緊迫している状態の人の場合は、優先的に申請を受理してもらえる可能性もあります。状況によっても審査の結果が出るまでの日数が変わってきます。
調査に時間がかかる特別な理由があるときは最長30日
調査の申請書類に不備があったり、特別な理由があると最長30日間かかることもあります。もし、30日を超えてしまった場合は却下された可能性が高いといえます。
調査結果について確認してみてもいいでしょう。
生活費がない場合、臨時特例つなぎ資金貸付を利用できる
生活保護の支給日までの生活費がない場合、臨時特例つなぎ資金貸付を利用できます。
福祉事務所にて申請したい旨を伝え手続きを行います。貸付限度額は10万円以内となり、連帯保証人や利子は必要ありません。
必要な書類を準備したうえで借入申し込みを行います。
・借入申込書
・公的給付や貸付の申請が受理された書類
・金融機関の預金通帳(本人)
・借用書
・印鑑
生活保護の申請で間違えやすいポイント

生活保護の申請で、間違えやすい注意点について説明します。
住んでいる場所がない人も生活保護の申請はできる
住居がなくネットカフェや車内、ホームレスでも、生活保護の申請ができます。
現在いる場所に近い福祉事務所にて相談してみてください。
住むところがないとはいえ、施設に入らないと申請できないわけではありません。必要な手続きも含め確認したうえで申請します。
持ち家のある人も生活保護の申請はできる
生活保護の申請は、持ち家がある人でも申請できます。
売却できる資産を活用することが生活保護の要件ではあるものの、持ち家はそのまま保有できる場合もあります。
必ずしも売却しないと生活保護の申請ができなくなるわけではありません。
書類がそろっていない状態でも申請できる
申告書を福祉事務所に提出していただく必要があるものの、特別な事情があるときは、申請書をかかずに申請を進めることもできます。
書類の準備を一人で行うのが難しい事情がある人もいるでしょう。書類がそろわないから生活保護の申請ができないわけではありません。
審査に通り受給したあとの対応も重要
生活保護の審査に通り受給をしたあとに、やらなくてはいけないこともあります。
受給している間は、毎月の収入の申告の義務が生じます。給与として受け取っているものはもちろん、年金や仕送りも対象です。謝礼や相続など受け取った収入のすべてが対象です。
申告を怠ると生活保護が打ち切りになることもあり、返還を求められる可能性も出てきます。また、年間数回程度の訪問調査があるのできちんと対応することも大切です。
審査に通らないときは何度でも再申請できる
生活保護の申請が通らないときも、何度でも再申請ができます。
回数の制限が設けられていないため、一度の結果で諦める必要はありません。ただし、却下されてしまった原因を解決しておかないと、同じ結果になってしまいます。
保護却下通知書には理由が記載されているため、参考にしつつ申請を行うようにしてください。
まとめ
生活保護の申請は、福祉事務所にて受給の意思を伝え審査に進めなくてはいけません。
審査には身辺調査や資産調査など必要に応じて行われるようになり、扶養照会で親族の意思の確認も行われます。事情によっては申請から受給までの期間が短くなることもありますし、扶養照会を行わずに進めることもあります。
ケースワーカーとの話し合いのなかで、今の状況や希望をきちんと伝えておくことが大切です。また、調査に必要な書類の提出など出来る限り協力的な態度で接するようにしていきましょう。
生活保護の受給後も、ケースワーカーに相談出来る関係性を作るようにしてください。
プロフィール

- 一般社団法人蓮華は高齢者様を一人にさせず、一人一人に対して真心を持って接していく会員制の団体です。 直面している社会問題を寄り添い共に考え、より良い未来を作り、 人生を豊かにしていくサポートを行っていきます。
最新の投稿
 生活支援お役立ちコラム2025.02.21一人暮らしの生活保護受給者が知るべき支援制度と毎月の金額の目安
生活支援お役立ちコラム2025.02.21一人暮らしの生活保護受給者が知るべき支援制度と毎月の金額の目安 生活支援お役立ちコラム2025.02.21生活保護で賃貸住宅を借りる際のポイントと家賃補助の仕組みを解説
生活支援お役立ちコラム2025.02.21生活保護で賃貸住宅を借りる際のポイントと家賃補助の仕組みを解説 生活支援お役立ちコラム2025.02.21生活保護は毎月いくらもらえる?収入と扶助内容の詳細を解説
生活支援お役立ちコラム2025.02.21生活保護は毎月いくらもらえる?収入と扶助内容の詳細を解説 生活支援お役立ちコラム2025.02.21生活保護医療券の使い方と注意点!受給者が知っておくべき医療サポート
生活支援お役立ちコラム2025.02.21生活保護医療券の使い方と注意点!受給者が知っておくべき医療サポート