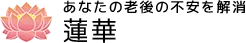生活保護の受給中に入院することになり、不安を感じている人もいるのではないでしょうか。まずはご自身の病気や怪我を治すことはもちろんですが、日々の生活費や入院費の支払いができるのか、心配になってしまう人もいると思います。
生活保護の受給者が入院になった場合、生活保護費はどうなるのか、また自己負担が発生するのかについて紹介します。急な入院で不安に思っている方も、必要な手続きやサポートの疑問を解決していきましょう。
生活保護の入院は医療費扶助の対象になる

生活保護は、生活に困窮しているすべての国民に対して、程度に応じて必要な保護を行い健康で文化的な最低限度の生活を保障するための制度です。
生活保護は受給者の状況に応じて、8つの扶助によって構成されています。毎月、生活保護受給者に支給されているのは「生活扶助」+「住宅扶助」の2つです。生活保護受給者の入院期間が1か月以内の場合、従来通りの住宅扶助+生活扶助が支給されるのが一般的です。
ただし、1か月を過ぎると、生活扶助が算定されなくなり「入院患者日用品費」が支給され収入が少なくなってしまいます。
医療費扶助で費用負担はほとんどない
生活保護受給中に入院になった場合、医療費扶助が適用されるため、入院費や入院中の食事について心配することはありません。入院中の健康的な食事は医療の一環であると考えられているため、しっかりと食事をとり治療に専念するようにしてください。
自治体から発行される「医療券」を医療機関に提出すれば、医療費を支払うことなく受診できます。
とはいえ、すべての医療機関で医療券が利用できるわけではなく、自治体で指定されている医療機関でのみ利用できます。対象の医療機関を知りたいときは、自治体のHPもしくはケースワーカーに相談するようにしてください。
自己負担が発生することもある
生活保護費は最低限の生活を保障する制度になるため、入院患者日用品費に切り替わると自己負担が発生してしまう人もいます。
入院患者日用品費はお住まいの地域に関わらず、一律23,110円が支給されます。なかには生活保護費以外に収入があり、23,110円を超えてしまう人もいるでしょう。
その場合、入院費以外は支給されなくなってしまい自己負担となります。
生活保護の受給中の入院で自己負担となる具体的な内訳を説明します。
個室代
生活保護の受給者は、基本的には安価な相部屋での入院となり医療扶助の対象です。個室の入院は贅沢品だと考えられているため、個人の希望による個室は自己負担となります。
とはいえ、個室しか空いていないときなど相部屋に入れない事情があると医療扶助の対象となり、自己負担が必要ないケースも考えられます。行き違いで個室を請求されるなどのトラブルに巻き込まれてしまう可能性もあるため、事前に確認しておきましょう。
病衣やスリッパ
病院によっても変わりますが、持ち込みの病衣やスリッパ、タオルを禁止している病院もあります。病院でリースとしてレンタルできるものの、自己負担で支払わなくてはいけなくなります。
セットレンタルとして日額でかかってくる病院もあるため、入院期間が長ければ長いほど費用負担が大きくなってしまいます。リース品のなかで、持ち込みで対応できるものがあるか、病院に相談してみてもいいでしょう。
おむつ
入院時におむつが必要になる場合、自己負担となる可能性があります。
おむつの場合、お住まいの自治体によっては、費用を負担してくれる場合もあります。自治体負担の場合、入院中は先払いしておき後から請求や返金での対応となることも少なくありません。
まずは、おむつが自己負担となるのか、ケースワーカーに相談し確認しておくと安心です。病院によっては病衣やスリッパなど必要なものをセットでリースになることもあります。
保険診療外の医療
医療扶助の対象となるのは、基本的には保険診療内で行った治療のみです。
例えば、生活保護受給者が癌になり入院した場合、抗がん剤やがんの摘出手術など治療に関わるすべての費用を、医療扶助にて賄うようになります。ただし、保険外の先進医療は医療扶助が適用されないため、注意してください。
保険診療外での治療が必要なときは、自己負担となるため事前に説明があるはずです。
住宅扶助が一定期間支給される
生活保護を受給している人の自宅家賃は、住宅扶助が一定期間支給されます。
ただし、入院中に生活保護の住宅扶助が支給されるのは、最長9か月までと決められています。病状によっては、退院の目途が立たない場合もあるでしょう。
入院期間が9か月を超えた場合は、入院基準に切り替わります。そのため、入院基準になり家賃の支払が追いつけない場合は、自宅の退去の連絡も必要になってきます。賃貸契約は、家賃を支払って成立している契約になるため、支払能力がないと住み続けるのが難しくなってしまいます。
無理に自宅を維持するよりも、余計な費用が掛かる前に判断し退去も検討してください。
入院患者日用品費は日割りではない
1か月以上入院していると、入院患者日用品費に切り替わります。支給される金額は一律で決まっており、23,110円と生活保護費よりも減額になる可能性が高くなります。
また、病気や治療の内容によって1か月以上入院する場合も少なくありません。この場合、日割りで計算されるのではなく、翌月の初日に生活扶助から入院患者日用品費に切り替えとなります。
障害者は加算もあるが申請が必須
精神障害者や知的障害者など、生活保護の受給中に病院で長期入院することもあります。
入院が1か月以上になると、生活扶助が算定されなくなり入院患者日用品費となります。障害者である程度重い症状で治療を受けていると、障害者加算の対象となります。
通常の生活保護費に加えてお金を受け取れるのもあり、支給額を増やせるようになります。ただし、申請しておかないと、加算の対象にならないため注意してください。
また、入院中の障害者加算は、最も支給金額の低い地域を基準に支給されます。
都心部に住んでいても、障害者加算の金額が安くなってしまう点は、覚えておきましょう。
生活保護の入院が長引いたときの注意点

生活保護の受給は、あくまでも自宅に住んでいると想定した金額で支給されています。
入院も一時的なものであれば、そこまで生活が大きく変わることはありませんが、長引くに連れて手続きや受け取れる生活保護費も変わってきます。
手続きのやり方も通常とは異なるため、福祉事務所やケースワーカーと相談しつつ進めていく必要が出てきます。
単身者
単身者の場合、入院が2週間~3週間程度であれば、今まで通りの生活扶助+住宅扶助が支給されます。
入院が1か月を越え長引くようになると、在宅基準の生活扶助が支給されなくなり、入院患者日用品費にて計上されます。
単身者の場合、自宅に誰も住んでいないため、生活扶助費が支給されなくなってしまい収入が減るため、注意が必要です。
家族世帯
家族世帯の場合、同居している家族が入院すると入院基準にて計算を行います。入院中は本人の生活扶助は支払が停止しますが、同居している家族の分はそのまま支給されるようになります。
本人の生活費が停止することで、全体の収入が減少してしまい生活が厳しくなってしまう可能性も出てきます。どうしても生活できない場合は、ケースワーカーに相談し支援について確認してみてもいいでしょう。
年金受給者
年金受給者の場合、入院すると生活基準から入院基準となり、生活扶助が停止となります。医療費や入院中の食事については医療扶助の対象となるため、自己負担はありません。
とはいえ、生活費は自己負担となり年金から賄うようになります。生活保護を受給していることで、税金や保険料の支払も免除されますが、入院中は受け取れる生活保護費が少なくなる可能性も出てきます。
退院後に覚えておきたいポイント

退院したあとに、いくつか必要になる手続きがあります。
退院後の生活も含め、覚えておいて欲しいポイントについて説明したいと思います。
住居を退去する場合家財保管料が支給される
生活保護を受給している人が住居を退去する場合、家財の保管や処分にかかる費用が支給される場合があります。
単身世帯で家財の保管が必要になる場合は、1年を上限に家財保管料が支給されることもあります。
ただし、他に支援手段がないことが条件となり誰でも支給されるわけではありません。退去後に、新しく入居するための家財を一時的に預けておける便利な制度です。
他にも、単身の受給者の場合、家財の処分が必要になるときに最低限の処分費用が支給されます。単身だと、他に片づけてくれる人がいないと想定されるための制度です。
原状回復費用は保護の対象外になるため慎重に検討
賃貸を退去するときに原状回復費用がかかることになります。
生活保護の対象外となるため、退去に必要な費用は自己負担となってしまいます。入居時に敷金をおさめておくことで、退去時にかかる費用を補うこともできます。
敷金をおさめずに入居している場合は、原状回復費の支払が必要になります。どうしても支払いが難しい場合は管理会社や大家さんに相談してみてから決める方法もあります。
部屋の状態によっては、高額な退去費が掛かる場合もあるので、使い方にも注意しましょう。
退院後の住居の準備も進める必要がある
入院中に、退院後の住居の準備を進めていく必要があります。
長期入院の場合、住居がなくなってしまいますし、賃貸契約には最低でも2週間程度の時間がかかることになります。とはいえ、生活保護の場合、すぐに住居が見つからないことも多く、審査に通らずに困ることもあるでしょう。
探してみてもどうしても見つからないときは、ケースワーカーに相談し住居の確保についてアドバイスをもらうようにしておきましょう。
早めに行動することで、退去後の生活を安定させることにも繋がります。
ケースワーカーに相談
退院の見通しがついたら、早めに準備を始めるようにしてください。入居までの部屋の準備や不動産会社と契約書類のやりとりなど、時間も必要になってきます。退院の目途が立ったときは、すぐにケースワーカーに連絡して新しい入居先を探してもいいか、相談するのをおすすめします。
退院したあとは生活扶助+住宅扶助の対象となるため、こまめに連絡をとるようにしておきましょう。
生活保護専用の不動産屋に相談
生活保護の賃貸物件探しは、審査面でも思うように進まず苦労することもあると思います。一般的な不動産会社の場合、紹介できる物件が少なく時間もかかります。退院も決まっているからこそ、できるだけ早く引越しを進めたいと考えている人もいるでしょう。
生活保護専門の不動産屋に相談することで、受給者でも入居しやすい物件を紹介してもらえます。生活保護ならではの手続きも熟知しているため、希望の物件を探しやすくなります。生活保護専用の不動産屋に相談することも検討してみてください。
まとめ
生活保護受給者が入院した場合、生活保護費はどう変わるのか?必要な手続きについても詳しく説明しました。入院中は住宅扶助が受け取れなくなってしまうため、賃貸物件を解約しなくてはいけなくなる場合もあるでしょう。
退院した後に再度物件を契約する必要もありますし、引っ越しにかかる費用も必要になります。ケースワーカーとの連携も非常に大切になるため、困ったことがあれば相談できるようにしておきましょう。
プロフィール

- 一般社団法人蓮華は高齢者様を一人にさせず、一人一人に対して真心を持って接していく会員制の団体です。 直面している社会問題を寄り添い共に考え、より良い未来を作り、 人生を豊かにしていくサポートを行っていきます。
最新の投稿
 生活支援お役立ちコラム2025.02.21一人暮らしの生活保護受給者が知るべき支援制度と毎月の金額の目安
生活支援お役立ちコラム2025.02.21一人暮らしの生活保護受給者が知るべき支援制度と毎月の金額の目安 生活支援お役立ちコラム2025.02.21生活保護で賃貸住宅を借りる際のポイントと家賃補助の仕組みを解説
生活支援お役立ちコラム2025.02.21生活保護で賃貸住宅を借りる際のポイントと家賃補助の仕組みを解説 生活支援お役立ちコラム2025.02.21生活保護は毎月いくらもらえる?収入と扶助内容の詳細を解説
生活支援お役立ちコラム2025.02.21生活保護は毎月いくらもらえる?収入と扶助内容の詳細を解説 生活支援お役立ちコラム2025.02.21生活保護医療券の使い方と注意点!受給者が知っておくべき医療サポート
生活支援お役立ちコラム2025.02.21生活保護医療券の使い方と注意点!受給者が知っておくべき医療サポート